どうもこんにちは。 ゆずです。
突然ですが、『お腹が痛くなると気分が落ち込む』『緊張するとお腹を壊す』『イライラを抑えられない』『頭では分かっているのに、感情をコントロールできない』
そんな経験、ありませんか?
考えたり、判断するときに人はどこが働いているのか‥…『脳』からの指令で行動を決めていると思いがちですが、それだけではありません。
『腸からの指令を脳が受け取り行動する』‥‥えっ??うそでしょ!!と思うかもしれませんが、本当です!なんとなく調子が悪かったり、はたまた調子が良い時って気にし過ぎなのでは?…と思いがちですが、
これは決して気のせいではありません。実は、私たちの脳と腸は密接につながっており、お互いに影響し合っているのです。この現象を「脳腸相関」と呼びます。
今日は、この不思議で興味深い脳腸相関について、分かりやすく解説していきましょう。
腸が「第二の脳」と呼ばれる理由
まず驚くべき事実から。私たちの腸には、脳に次いで多くの神経細胞が存在しています。その数はなんと約1億個!これは脊髄よりも多い数字です。
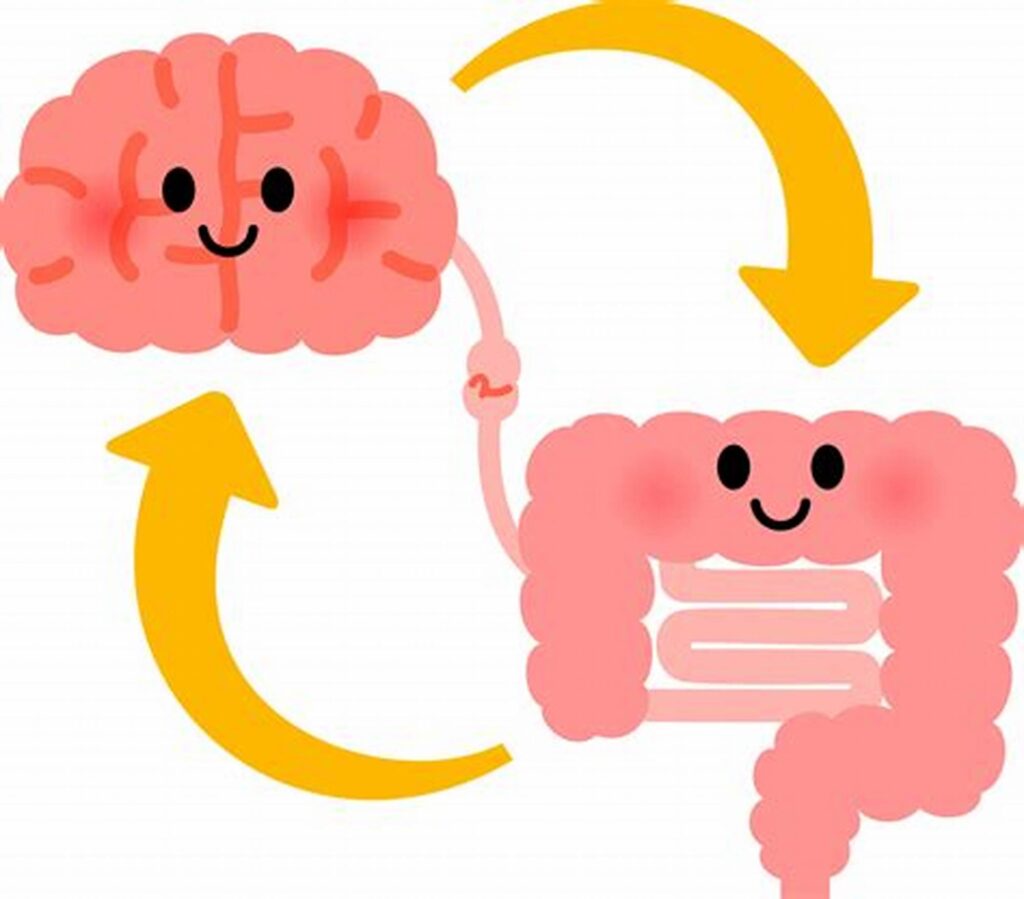
腸の壁には「腸管神経系」という独自の神経ネットワークが張り巡らされており、この神経系は脳からの指令がなくても独立して機能することができます。
つまり、食べたものをエネルギーとする作業は、脳ではなく、『腸管神経』が独自に働いていると言われています。
腸は単なる消化器官ではなく、まさに「考える器官」なのです。
脳と腸をつなぐ3つのルート

脳と腸は、主に3つの経路を通じてコミュニケーションを取っています。
1. 神経系ルート(迷走神経)
迷走神経は脳と腸を直接結ぶ高速道路のような存在です。この神経を通じて、脳と腸は瞬時に情報をやり取りしています。
腸の蠕動運動や消化液の分泌を制御する一方で、腸からの感覚情報を脳に送ります。ストレスを感じると胃が痛くなったり、緊張で下痢になったりするのは、この神経を通じた脳腸相互作用の典型例です。
2. ホルモンルート(内分泌系)
腸で作られたホルモンが血液を通じて脳に届けられ、逆に脳で作られたホルモンが腸に作用します。
代表的なものにセロトニン(約90%が腸で産生)、GLP-1(食欲抑制に関与)、グレリン(空腹感を促進)などがあります。これらのホルモンは気分、食欲、満腹感などを調節し、脳の視床下部や大脳辺縁系に作用します。
『幸せホルモン』と呼ばれているセロトニンやドーパミンなどのの約90%は、実は腸で作られているのです。
3. 免疫系ルート
腸内細菌が作り出す物質が免疫系を介して脳に影響を与えます。食物繊維を発酵させて産生する短鎖脂肪酸(酪酸、プロピオン酸、酢酸など)や、細菌が産生する神経伝達物質様の化合物が血流を通じて脳に影響を与えます。
これらの代謝産物は血液脳関門を通過し、神経炎症の抑制や神経伝達物質の産生に関与することで、腸内環境の変化が全身の炎症レベルに影響します。
それが脳の機能にも波及するので、認知機能や気分に影響を与えます。
日常生活で感じる脳腸相関
ストレスとの関係
【重要なプレゼンの前にお腹が痛くなったり】【試験前に下痢になったり】【休日になるとたくさん食べれるようになること】……これって脳が感じたストレスが腸に直接影響を与えているからです。
ストレスホルモンのコルチゾールが腸の動きを活発にし、消化機能に影響を与えるのです。
腸内細菌と性格
最近の研究では、腸内細菌の構成が性格や行動にも影響することが分かってきています。特定の腸内細菌が多い人は社交的になりやすく、別の細菌が多い人は内向的になりやすいという報告もあります。
腸内環境が心の健康に与える影響
うつ病との関連
うつ病患者の腸内細菌を調べると、健康な人と比べて多様性が低く、特定の有害菌が多いことが分かっています。腸内環境を改善することで、うつ症状が軽減される可能性があります。
不安症との関係
慢性的な不安を抱える人の多くが、腸内環境の乱れを併発しています。腸内細菌のバランスが崩れると、不安を感じやすくなる神経伝達物質の産生が影響を受けるためです。
脳腸相関を改善する実践的な方法

1. 食生活の見直し
- 発酵食品を積極的に摂取:ヨーグルト、キムチ、味噌、納豆などの発酵食品は善玉菌を増やします
- 食物繊維を豊富に:野菜、果物、全粒穀物は腸内細菌のエサになります
- プロバイオティクス・プレバイオティクスの活用:善玉菌そのものと、そのエサとなる成分を摂取しましょう
2. ストレス管理
- 深呼吸や瞑想:迷走神経を刺激し、リラックスモードを促進します
- 適度な運動:腸の蠕動運動を促進し、ストレス解消にも効果的です
- 十分な睡眠:腸内細菌は睡眠リズムに合わせて活動しています
3. 生活習慣の改善
- 規則正しい食事時間:体内時計を整えることで腸内環境も安定します
- 水分補給:適切な水分摂取は腸の動きをスムーズにします
- 過度な抗生物質の使用を避ける:必要以上の抗生物質は善玉菌も殺してしまいます
まとめ:人生においての食の見直しから始まる腸活

いかがでしたか。
脳腸相関は、私たちの心と体の健康を理解する上で欠かせない概念です。「お腹の調子が悪いと気分も優れない」のは、科学的に説明がつく現象だったのです。
あと大事なのが皆で食事を共有することです。出来れば手料理を食べる。
『手料理を食べると幸せな気分になる』いわゆる家庭の味と言えばよいでしょうか。外食するのが当たり前になっている現代社会において、手料理を味わう機会は昔と比べて少なくなっています。
もちろん美味しい外食はたくさんありますし、お腹も満腹にさせてくれます。お昼休みをコンビニで購入したり、忙しいから食事の時間を割いて、作業をしながら食べている人もいるかと思います。
これは個人の意見ですが、外食含めるジャンクフードを取りながら食事の時間を割く生活で心が豊かになるのかということです。
遅くまで塾で勉強している学生が帰宅時にジャンクフードを食べているのをみたときに『食』の重要性が現代人には失われている気がしてならないのです。
一見『脳腸相関と関係ないじゃん』と思えるかもしれませんが、誰と何を食べるのかということは脳と腸に大いに関係します。お腹は満腹に出来ても心が豊かにならなければ意味が無いのです。
【人は何のために食べるのか‥‥】そのことが根本にあるからこその『腸活』なのです。
美味しいものを皆で共有しながら食事を取る‥‥もちろんできない方も多いでしょう。
- 大手チェーンの外食ではなく、個人経営の定食屋に行く
- たまには自宅でご飯とみそ汁と漬物だけ摂取する
- 簡単で構わないので火を使った手料理を食べる
- 居酒屋で皆と楽しみながら食事をする
- ジャンクフードはなるべく避ける
まずは心が豊かになるような【食】から始めてみましょう。
余裕ができたら、発酵食品を意識的に取り入れたり、ストレス管理を心がけたりすることです。腸内環境を改善し、それが心の健康にもつながります。
【こちらもおすすめです】
あなたの「第二の脳」である腸を大切にケアすることで、より豊かで健康的な生活を送ることができるでしょう。
この記事は現在の科学的知見に基づいて作成されていますが、健康に関する具体的な悩みがある場合は、必ず医療専門家にご相談ください。


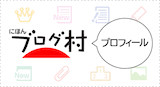


コメント