こんにちは、ゆずです。
『甘いもの』が今回のテーマです。
10代の頃は、甘いものが好きでしたが、20代の半ば頃から甘いものが苦手になっていきました。食べれないわけではないのですが、食べても満腹感というか達成感が感じられなくなってしまったのです。
今ではバニラアイスのカップを平らげることもできません‥‥おかげで家族内でデザートに対する不協和音が生じることはありませんが・・・。
一口二口まではいけますが、それ以上になると喉の渇きと不快感がどうしても出てきてしまうのです。最初のうちは、頭が冴えて身体が軽くなる感じがあるのですが、その後にだるい感じが出てくるので、それが不快感の正体ですね。
世の中には甘いものが好きな方が数多くいます。もしかしたら甘いものが嫌いな方のほうが少ないかもしれません。
それだけ甘いものには魅力が詰まっているのでしょう。でもですね‥‥甘いものを摂取することはリスクも備わっています。
今日は私たちの日常に深く関わる「甘いもの」について、身体への影響を詳しく見ていきましょう。
砂糖による即時的な影響

疲れた時に『甘いものを欲する』人は多いのではないかと思います。手が届くほどの身近な場所にお菓子を置いている人‥…多いです。
甘いものを摂取することで、血糖値が急上昇します。これにより、一時的なエネルギー増加を感じることができるので、頭が冴えたり、元気がでたりします。これが「砂糖の高揚感」というものです。
ですが、この『砂糖の高揚感』は残念ながら長続きはしないのです。身体には、無意識に内部環境を一定に保つように働いています。いわゆる『恒常性を保つ』です。
甘いもの摂取による血糖値の急上昇が起こると、恒常性を保つためにインスリンが分泌されて血糖値を下げようとする働きが起こります。結果、約30分〜1時間後には「クラッシュ」と呼ばれる疲労感や集中力低下が訪れることがあります。
疲労感や集中力低下が起きる→甘いもの摂取→一時的回復→疲労感や集中力低下が起きる→甘いもの摂取
このように甘いもの摂取の無限ループに陥るのです。
長期的な影響

体重増加
『わかっちゃいるけど、やめられない‥‥』。
痩せたいけど痩せれない人は、ほぼこのような思考から脱却できない方々です(笑)特に甘いものに関しては依存度が高い分、体重増加につながるケースが多いです。
【甘いもの摂取→血糖値急上昇→インスリンによる血糖値下降→余剰な糖分を脂肪として貯蓄】‥‥‥。これが体重増加の原因です。
また、砂糖は高カロリーでありながら栄養価が低く、過剰摂取は容易に余分なカロリーとなります。特に砂糖入り飲料は満腹感をあまり与えないため、知らず知らずのうちにカロリーオーバーになりがちです。
ちなみにスーパーやコンビニで販売されている飲料水には、ほぼ人工甘味料や果糖ブドウ糖が使われています。(成分表の確認をおススメです。)
【こちらも参考にしてください】
歯の健康
【甘いものを食べると虫歯になる…】誰もが認識していることですが、
『でも実は、虫歯の大半の原因って他にあるんじゃ‥‥』のように甘党の立場からすると陰謀論を唱えたくなるかもしれませんが、甘いもの=虫歯…全くその通りです。
砂糖は虫歯の主要な原因です。口内の細菌(虫歯菌)が砂糖を分解する際に酸を生成し、この酸が歯のエナメル質を溶かして虫歯の原因となります。
ちなみにもっとも虫歯のリスクが高いお菓子は、キャンディーやキャラメルです。砂糖の保有量、粘度の高さ、食べるのに時間を要することが虫歯菌を活発に働かしてしまうのです。
肝臓への負担
過剰な砂糖、特にフルクトース(果糖)は肝臓で処理されます。ここで言う果糖というのは、果糖ブドウ糖駅糖や高果糖液糖などの添加物を指します。
:果糖ブドウ糖駅糖や高果糖液糖が含まれている主な食品
- 清涼飲料水(コーラ、炭酸飲料、スポーツドリンクなど)
- 缶入りや瓶入りのお茶・コーヒー飲料
- フルーツジュース(特に加工された100%ではないもの)
- ヨーグルト(特に果物風味の甘いタイプ)
- アイスクリームやフローズンデザート
- ジャムやシロップ
- 菓子パンやケーキ
- クッキーやビスケット
- シリアル(特に糖分の多いタイプ)
- キャンディーやチョコレート
- ドレッシングやソース類(特に甘味のあるもの)
- 加工肉製品(ハムやソーセージなど)
- 缶詰フルーツ(シロップ漬け)
こうして見てみると、日常で口にするものばかりです‥…。

天然の果物には果糖はもちろん含まれています。しかし同時に食物繊維、ビタミン等の栄養素が豊富な為、果糖の吸収を緩やかにしてくれるので、果物を適量食べる場合は問題ありません。(とは言っても過剰の摂取すれば害が出る可能性がある…)
継続的な高摂取は脂肪肝などの肝臓疾患リスクを高めます。
炎症と免疫機能
過剰な砂糖は体内で炎症反応を促進していきます。筋肉痛がひどい方、肉離れされた方、骨折された方、治りを促進させるには、糖分の摂取を極力控えることです。
また、糖(特に精製糖や加工食品に含まれる添加糖)による過剰摂取には免疫システムの機能を一時的に低下させることがあります。
脳への影響
砂糖は脳内の報酬系に作用し、ドーパミンを放出させます。これが「砂糖中毒」と呼ばれる状態を引き起こすことがあります。また、継続的な高砂糖食は認知機能に悪影響を与える可能性も示唆されています。
砂糖摂取を減らすためのヒント
- 飲み物を見直す:清涼飲料水やスポーツドリンクには大量の砂糖が含まれています。水や無糖のお茶に切り替えましょう。
- 食品ラベルをチェック:多くの加工食品には「隠れ砂糖」が含まれています。原材料表示を確認する習慣をつけましょう。
- 天然の甘味に移行:果物の自然な甘さで砂糖欲を満たす方法も効果的です。
- 徐々に減らす:急激な変化は難しいため、少しずつ砂糖摂取量を減らしていきましょう。
まとめ:砂糖の見直し

いかがでしたか?
もともと人の身体は砂糖を摂取するのに適していないと言われています。依存度も高い砂糖に身体が頼ってしまうことで、身体の恒常性を保つことが困難になり、免疫が低下し、細菌に感染しやすくなり、アレルギーになりやすくなります。
砂糖を完全に排除する必要はありませんが、意識して適量を心がけることが健康維持の鍵となります。自分の体調と相談しながら、バランスの取れた食生活を目指しましょう!
皆さんの健康な毎日を応援しています。次回もお楽しみに!
体質改善ダイエットランキング


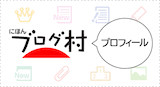


コメント