どうもこんにちは ゆずです。
突然ですが、わたしは歴史が好きです!鎌倉時代に元寇で元軍を返り討ちにした武士たちには畏敬の念を抱いております。※元軍を返り討ちにした部分だけですが…
一説には諸外国から恐れられていた日本の武士。そんな武士の日ごろの鍛錬はどのようなものかと興味を抱きましたので、簡単ではありますが調べてみました。
武芸の鍛錬:
- 弓術(弓馬術):馬上からの射撃を含む弓の技術
- 剣術:刀の扱いの練習
- 槍術:槍を使った戦闘技術
- 馬術:戦場での機動性を高めるための乗馬技術
身体鍛錬:
- 筋力トレーニング:重い武具を装備して戦うための体力づくり
- 持久力の向上:長時間の戦闘に耐えるための訓練
- 水練(水泳):川や海での戦いに備えた水中での動きの練習
精神的鍛錬:
- 座禅:集中力と精神統一のための修行
- 文武両道:漢詩や和歌の学習なども武士の教養として重視
実戦的訓練:
- 流鏑馬(やぶさめ):馬上から的を射る訓練
- 打ち込み稽古:木刀や竹刀を使った対人稽古
- 集団戦術の練習:陣形の維持や指揮系統の確認
『日常で取り入れられる鍛錬はないものか…』
気軽にできそうなのは‥‥打ち込み稽古!
『対人稽古は難しいので素振りをやってみよう!』
というわけで竹刀の素振りにを初めてみました。わたしの場合は竹刀だと自宅の天井に当たるので代用品としてこちらを使用しています!👇👇

2キロの重りです(笑)
※ホームセンターで偶然見つけました。
そして、早速素振りを実行してみました…
身体の筋肉痛(特に上半身が)半端ないです!!
細かい筋肉まで無駄なく鍛えられているのが分かります!素振りを終えた後は、有酸素運動をやり終えた感覚と似た疲労感があります!
そんな素振りの効果と魅力を紹介していきます。
竹刀の素振りの起源
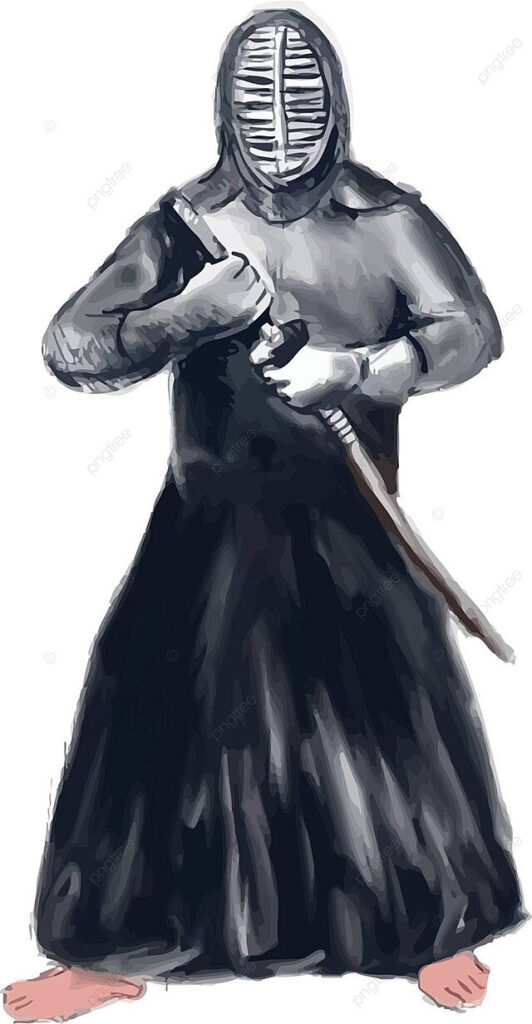
竹刀の素振りの起源については、剣道の歴史と深く関わっています。
素振り自体は日本の剣術の伝統的な練習方法で、元々は実際の刀や木刀を使って行われていました。これは武士が実戦に備えて技を磨くための基本的な稽古でした。
竹刀(しない)が広く使われるようになったのは江戸時代中期から後期にかけてと言われています。1711年頃、直心影流の中西忠蔵が防具と共に竹刀を考案したとされています。
それまでの木刀による稽古では怪我の危険が高く、より安全に打ち込み稽古ができる道具として竹刀が普及していきました。
竹刀を使った素振りが一般的になったのは、明治時代に入ってからです。1895年に大日本武徳会が設立されると、剣道の稽古法がより体系化され、竹刀による素振りも基本の練習法として確立されていきました。
現代の形で竹刀の素振りが定着したのは、学校教育に剣道が取り入れられるようになった大正から昭和初期にかけてだと言われています。この時期に剣道の指導法が標準化され、竹刀での素振りが基礎トレーニングとして重視されるようになりました。
素振りは単なる技術練習ではなく、精神修養の側面も持つとされ、日本の武道精神を体現する練習法として今日まで継承されています。
素振りによる効果

素振りと言われてイメージするのは、剣道の基本トレーニングではないでしょうか。
単調に見えるこの練習には、実は多くの効果が隠されています!
今回は竹刀を使った素振りがどのように身体に良い影響をもたらすのか、詳しく解説します。
筋力・持久力の向上
数百回の素振りを行うと腕、肩、背中の筋肉に大きな負荷がかかります。
この負荷は、ランニングのみでは得られない身体全身の持久力が身につきます。
私の場合、毎朝100回の素振りを1ヶ月続けておりますが、変化といえば懸垂が10回できるようになりました!
※1回行う毎に肘を伸ばしての懸垂です。
↑↑これには本当に驚きました!
ゆっくり行なう懸垂は全身の持久力がないと困難だと言われています
また素振りによる単調な動作のトレーニングには、深い集中力を養う効果があります。
一打一打に意識を集中させ、呼吸と動作を一致させることで、精神の安定と集中力の持続が鍛えられます。
「心技体」の要素を含んでいる素振りは、身体トレーニングだけではなく、心と技を磨くトレーニングでもあるのです。
素振りによって鍛えられる筋肉:
上半身
- 前腕の筋肉(橈側手根屈筋・尺側手根屈筋): 握り続けることで鍛えられます
- 上腕二頭筋・上腕三頭筋: 振り上げ、打ち下ろす動作で使われます
- 三角筋(肩): 特に前部・中部三角筋が持ち上げる動作で活性化されます
- 僧帽筋: 肩甲骨の安定と動きをサポートし、特に上部僧帽筋が素振りの際に働きます
- 広背筋: 打ち下ろす動作の際に大きく関与します
- 胸筋(大胸筋): 前に出す動作で使われます
- 脊柱起立筋: 正しい姿勢を維持するために重要な背中の筋肉
下半身
- 大腿四頭筋: 前足を踏み込む際に使われる太もも前面の筋肉
- ハムストリングス: 打ち下ろし時の姿勢保持と後ろ足の蹴り出しに関わる太もも裏側の筋肉
- 大臀筋: 腰の安定と力の伝達の際に刺激が入ります
- 下腿三頭筋(ふくらはぎ): 踏み込み動作や足さばきで使われます
コア(体幹)
- 腹直筋・腹斜筋: 上半身と下半身の力を連動させる際に重要で、打ち下ろす際に自然と力が入ります
- 腸腰筋: 股関節の屈曲と体幹の安定に関わり、正しい姿勢と打ち下ろす動作で力が入ります
こうしてみるとほぼ全身を鍛えられることがわかりますね!
基本姿勢

基本的な素振りのやり方を段階的に説明します。
- 構え方: 両足を肩幅程度に開き、右足を少し前に出します(右利きの場合)
- 中段の構え: 竹刀の切っ先を相手の喉あたりに向け、両手を臍の高さで構えます
正面素振りの基本動作
- 振り上げ:
- 両手を頭上に上げ、竹刀(または代用品)が背中と平行になるくらいまで振り上げます
- このとき、両肘を曲げず、手首も曲げないようにします
- 打ち下ろし:
- 竹刀を真っ直ぐに降ろします
- 「メン!」と声を出しながら行なうと良いらしいですが、私はしてません(笑)
- 手首のスナップを効かせず、肩から腕全体で振り下ろします
- 振り上げと打ち下ろしを繰り返す:
- リズムを一定に保ちながら、10回、30回、100回と徐々に回数を増やしていきます
足さばきを加えた素振り
- 送り足素振り:
- 振り上げるときに左足を右足に近づけます
- 打ち下ろすときに右足を一歩前に踏み出し、左足を引き付けます
- この動作を繰り返します
- 踏み込み素振り:
- 振り上げた後、打ち下ろすと同時に右足を大きく踏み込みます
- 左足も引き付けて前進します
- 素振りの度に一歩前進するイメージです
※足さばき無しで振り上げと打ち下ろしを繰り返すだけでも効果があります
応用素振り
余裕があれば、以下の応用素振りも練習するとよいでしょう:
- 左右面素振り: 左右の面(頭部の側面)を打つ素振り
- 千回素振り: 正面素振りを千回連続で行う持久力トレーニング
↑↑これはかなりの覚悟が要ります(笑)
素振りの注意点
- 背筋を伸ばし、姿勢を正しく保ちましょう
- 竹刀を振る際は、手首だけでなく肩から腕全体を使います
- 力を入れすぎず、自然な動きを心がけます
- 呼吸を意識し、打ち下ろしのタイミングで息を吐きます
- 毎日継続して行うことが大事です
まとめ:精神と身体を鍛える素振り

単調に思える素振りですが、その効果は計り知れません。
日本人が発案する鍛錬(トレーニング)は体力向上はもとより精神力も鍛える内容が多いものばかりです!
素振りもその一つです。
何か行動を移すときに大事なのは、まずは身体です。そして物事の本質を見極め、正しい判断をするには精神が正常に働いていることが求められます。身体と精神を鍛えることで人生はとても豊かなものになります!
豊かな人生を手にするためにまずは、素振りを取り入れてみてはいかがでしょうか‥!!!
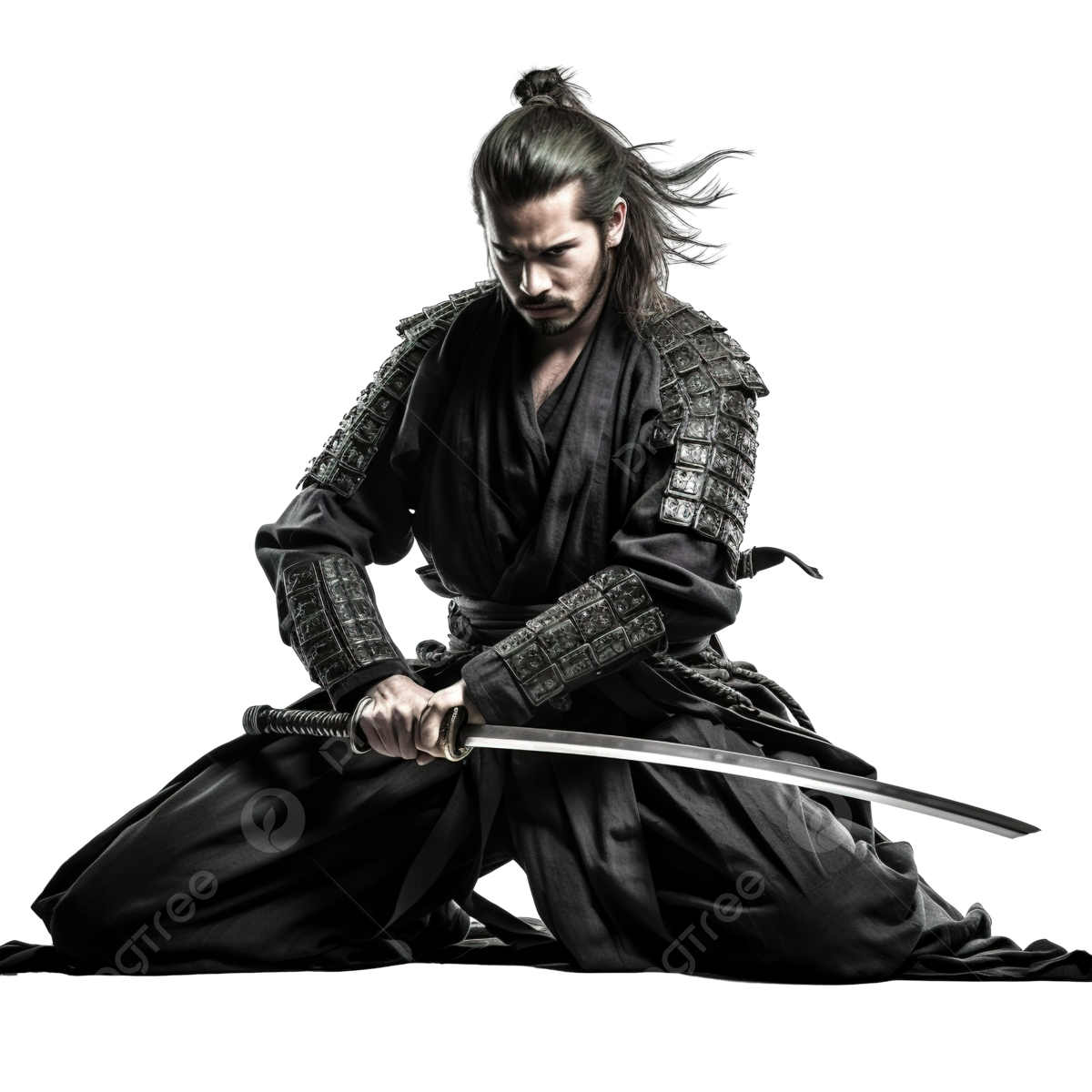
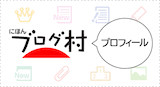


コメント