『こんなに頑張っているのに評価されない….』
『良かれと思ってやっているのに全然褒められない』
ついつい他人に期待をしてしまい、自分が思っていた感謝や評価がされないことはたくさんあるかと思います。
『期待に応えるのはやめよう』
『どうせ頑張っても評価されないから適当に業務をこなそう』
目標に対しての行動意欲がどんどん薄れていき、心が少しずつ荒んでいくようになります。そうして愚痴が多くなります。
愚痴が多い人は聞かされている側からすれば気持ち良いものではないので、徐々に遠ざけようとしてきます。
そうしてますます愚痴が多くなり、憎悪感が増してきて最悪な場合他人に対して攻撃的になってきます。

あいつムカつくな!

こんなにやっているのになんであいつだけ良い思いするんだよ!

結果が出ているのもたまたまじゃね~か!!
当たり前ですが、こうならないようにしよう…と心の中で思っていても、こんな感じの場面は誰しもが一度は経験しているのでないかと思います。もちろん私もあります。
『だって人間だもん…』
と相田みつをのセリフを吐いてしまいたいくらい、やけくそになってしまいます(笑)
では何故このような負のオーラをまとってしまうのでしょうか。
それは『他人に期待をしてしまっている』からではないかと思います。
芸能人のタモリさんがこんな言葉を残しています。
オレは何事にも期待していないところがあるんだね。(中略)
オレは人間性に対して信頼をおいていない。
他人に期待などしなければ、つまらないことで感情的にならずにすませることができる。
こうすれば人間関係に波風も立たなくなり、円満にだれとでも付き合えるのである。
良い悪いは別にして真理をついている言葉だなと思いました。
他人に期待をすることは他人からどうみられたいかという心理状態が働いてしまっているからではないでしょうか。
『好かれよう』
『これをやれば喜ばれるはずだ』
そうなると八方美人になってしまい、自分が疲れるようになります。八方美人がダメとは言いませんが、やりすぎはよくないです。何事もそうですが、やりすぎ行為は徐々に身体と精神を削ってしまい不調をきたします。
たまには他人に期待をしないことをおすすめします。
他人に期待をしないとどんなメリットがあるでしょうか。
他人に期待をしないメリットとは

1. 心の平和を保ちやすくなります。
誰でも嫌なことはなるべく避けたいです。それでも自分ではどうしようもない嫌なことが訪れるときはあります。そのときに他人に頼りたい(期待したい)気持ちが生まれます。結果、結局嫌なことが訪れ、他人にせいにします。
他人のせいにしたときの心って、必ず後々振り返ると自分に対して嫌悪感が生まれ、引きずりやすくなります。嫌悪感は他人に期待をしたからこそ生まれたものです。
『嫌なことがあるけど、しょうがない‥‥』
こうやって受け入れることで嫌なことは結局訪れますが(笑)そこで終了します。
心を余計に乱されることがないので、引きずることもないし、精神状態は以外と平和の状態の均衡を保てるものです。
2. 日々の出来事に感謝と喜びが感じやすくなるので毎日が楽しい
『上手くいくかどうかわからないけど、とりあえずやってみるか』
『上手くいかなくても死ぬわけじゃないから気軽にやるか』
『失敗してもしょうがない‥‥』
このような感じで大きな期待を持たずに遂行することで上手くいった時や良いことが起きた時により大きな喜びを感じられます。また予想外の幸せな出来事に対して純粋に驚き、感謝できるようになります。
また期待をしないから失敗を受け入れやすくなります。これは今を集中することに繋がりますので、結果的に物事がうまくいくようになります。
4. 嫌味をいわれなくなる
嫌味を言われる人の特徴って
- 常にペコペコしている。
- おべっかを使いすぎてる。
- 気を遣いすぎている
- 常に謝っている
こういう人は他人にどう見られたいか(期待)という考えに縛られている傾向があります。嫌味を言う人はこういった人を好みます。(要は自分より下に人)
期待をしない人は真逆でそういった考えに縛られることがないので、いい意味で固定観念を取り払らえています。
『この人を怒らしたらまずい』
『この人により気を使おう』
こんな感じのマインドが薄れていくので、嫌われることはなくても好かれることもないような立ち位置を形成しやすくなります。嫌味を言う人は基本自分に共感している人を好むので、期待をしない人には近づいてきません。
このポジションになると人間付き合いが非常に楽になります。帰りたかったら帰れるし、無理な付き合いをしないから相手の嫌な部分を見る機会が減るので、心が穏やかに日々を過ごせるようになります。
5.新しい事への発見を見出す
『期待はしていないけど、目の前のこと頑張っている人』が条件になりますが、
こういった方は自身で情報を仕入れて行動を開始するケースが多いです。
『今やってることを頑張りつつ、転職サイトに登録して自分に合う仕事探し』
『ブログを活用してライティングスキルを磨く』
仕事を例にいえば本業以外に何かをしていることですね。
他人に向上の期待をすることなく、自分の判断で行動するので、
新しい可能性に気づきやすくなりまし、予想外の方向性や解決策を見いだせるようになります。
6. ストレスの軽減
これが一番のメリットといえるかもしれません。
期待をしない人は「〜であるべき」という概念が減少するため、精神的な負担が減ります。
『とりあえずあるがままを受け入れよう』
『やっちまったらしょうがないし、それも人生だ』みたいな姿勢で臨むことでストレスを軽減しています。
勘違いしてほしくないのは期待しないことは、決して諦めることではないということです。
現実をより冷静に受け止め、よりよい未来のために柔軟に対応する姿勢という表れになります。
期待をしないことのメリットに関する心理学的メカニズム

期待をしないことへのメリットに関する心理学的な観点からの作用について説明します。
- 認知的不協和の軽減
期待と現実の間にずれが生じると「認知的不協和」という心理的不快感が生まれます。期待を持たないことで、この不協和状態を避けることができます。 - ヘッジング理論
心理学では「感情的ヘッジング」と呼ばれる防衛機制があります。これは最悪の結果を想定して心の準備をすることで、実際に悪い結果になった場合の衝撃を和らげる戦略です。 - マインドフルネスの促進
期待は未来に意識を向けさせますが、期待を手放すことで「今この瞬間」に集中しやすくなります。これは心理療法でも重視されるマインドフルネス状態を促進します。 - レジリエンスの向上
期待しないことで、予期せぬ状況に対する心理的な回復力(レジリエンス)が高まります。変化に対して柔軟に対応できる精神的強さを養います。 - 自己効力感への影響
期待を持たないことは、時に自己効力感(自分の能力への信頼)を高めることがあります。なぜなら、外部要因への依存が減り、自分の行動に集中できるからです。 - 心理的免疫システム
心理学者ダニエル・ギルバートが提唱する「心理的免疫システム」によれば、人間は悪い出来事に対して自然に適応するメカニズムを持っています。期待を持たないことでこのシステムがより効果的に機能します。 - フロー状態への接近
心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱する「フロー状態」(活動に完全に没頭している最適な心理状態)は、結果への期待よりも過程自体に集中することで達成されやすくなります。 - 社会的比較の減少
期待を持たないことで、他者との比較に基づく自己評価が減少し、心理的な幸福感が向上することがあります。
まとめ:期待をしないことは自分のため

期待しないことが単なる諦めではないということと同時に自分を助けることになります。
とは言っても人間どこかで他人に期待はしている生き物です。
過剰に他人に期待をするのは申し上げたとおりですが、かと言って期待しなさ過ぎても向上心低下を招きます。大事なのはバランスです。
精神的健康と心の平和を促進する積極的な心理戦略が一番の目的なのでそこを見失わないことを心掛けてみてください。
↓↓合わせてどうぞ


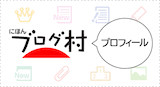


コメント